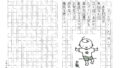京都に長岡禅塾という道場があって、そこに森本省念老師という素晴らしい方がいらっしゃいました。
型にはまった禅僧ではなくて、浄土宗のお寺の寺男のようなことをされたり、天理教にご縁があったり、カトリックの勉強をされたこともあり…、ということで、心が開けた柔軟自由な精神の方で、悟りの境地を自在にコトバを操って(禅の用語を使わなくても)表現できる達人でした。丁度、趙州禅師のような方ですね。
私は省念老師に直接お会いしたことはありませんが、私の師匠のうちの一人である渡辺玄道老師は、若い頃に省念老師とお会いしたことがあると、その体験を語っておられました。
玄道老師は熱血漢(なんせ侠客の大親分の孫ですからね)でしたから、禅界が衰えて堕落していることや、日本や世界の現状が嘆かわしいといったようなことを、とても憤って省念老師に訴えたらしいのですが、省念老師は、「仏法ますます繁盛ということやがな」と言って、笑っておられたそうです。
分かりますか?
仏法というものは、禅というものは、高尚で、清らかで、悟りきったものではないのです。地上世界を離脱して、「そんなの関係ねえ」とお高く留まっているものでもないし、高処から下界を見下ろして、「けしからん」と慨嘆するといったものでもないのです。
仏法でも、禅でも、確かに入門してくる人は、清らかで高い境地を目指し、泥だらけの地上世界から脱出したくて修行を始めるわけですが、結局のところは、その獲得した悟りの境地(?)を一切合財、エイッと放り出して、もう一度、地上世界のみんなの処に帰ってくるのです。
そして、みんなと泥んこ、一緒くたになって、どれが人やら、どこまでが自分やら分からないくらい混じりあって暮らすのです。そこにこそ禅の究極の境地があります。
仏法というもの、禅というものの本質はそういうもので、泥だらけ、矛盾だらけの現実社会でウロチョロ、戸惑いながら生きている、そんなありのままの自分のすべてを肯定し、人を肯定し、世界を肯定して、そのすべてを温かく抱きしめ、ひとつに包み込んでゆく。その抱擁こそが禅の、仏法のすべてなんです。
その「愛の抱擁」は、世界の泥んこが激しいほど、怒りや嘆きや悲痛が大きくなるほど、ますます力強い、確かなものになってゆきます。
ですから、混沌が深まり、人類の惑いが激しくなるほど、「仏法ますます繁盛」なのです。
親鸞さんは「善人でも救われるのであるから、悪人ならなおさらのこと救われるのだ(善人なおもって往生をとぐ、いはんや悪人をや)」(『歎異抄』)とおっしゃいました。
善人もこの「愛の抱擁」に抱きしめられており、いわんや悪人に対しては、なおさらのこと、その抱擁はしっかり強く大きなものにならざるを得ないのです。
このように、禅でも浄土宗や浄土真宗でも、キリスト教でも、天理教でも、その究極のところはみんな同じです。この「愛の抱擁のみ」です。
それ以外のことは、すべて枝葉です。
禅の人は、禅が他宗に比べ最高のものなのだと誇り勝ちです。
禅の伝統といい、教育指導法といい、とてもよく工夫された、日本的霊性の精緻といっていいほど素晴らしいものなのですが、実はそれらも禅の本質ではなく枝葉のものにすぎないのです。
それらの先人が苦労の末に生み出された素晴らしい「型」を、その「型」のまま、維持し伝承してゆくことがもっとも大切なことなのだと、禅の世界の人は思いがちです。
そんな江戸時代や鎌倉時代に出来た「型」は、時代の変遷とともに、衰えて失われてしまったとしても、少しも憤ったり、嘆いたりする必要はないのです。
禅の本質は「愛の抱擁のみ」なのですからね。
その愛の本質が、人類の混乱や惑いの時には必ず発動して、その時代と人にふさわしい新しい「型」がまた次々生み出されてくるのですから。
「アンタが心配せんかて、朝がくればちゃんと東の空にお日さんが昇ってくるがな」ということですね。
この省念老師と渡辺老師の対談の話とそっくりの公案があるので、紹介しておきましょう。それは、「文殊前三三」という公案で、『碧巌録』の第三十五則に出てきます。
この公案は、以前どこかで紹介して解説もさせてもらったと記憶しているのですが、公案というものは、そのそれぞれの時期や環境や年齢によって、また違った納得や理解があるものですから、もう一度勉強しておいてもいいですね。
無著禅師の若い頃の話です。
無著さんが五台山(文殊菩薩の霊場)の山中で道に迷って歩いていると、目の前に見知らぬ禅寺が現われたのです。
『あれ、こんなところにお寺があったっけ?』と不思議に思ったのですが、もう夜になっていましたから一夜の宿を借りようと、門を入って行きました。
すると、童子がいて、事情を説明したところ、住職の方丈(居室)に案内されました。
住職(実は文殊菩薩であることが後ほど判明する)は無著さんに尋ねます。
住職「どこから来たのかね」
無著「南方から来ました」
住職「南方の仏法はどんな様子かな」
無著「悲しいことに、もう末法の状態で、すっかり衰退堕落してしまいました。ほんのわずかな僧だけが戒律をまもって修行しています」
住職「そんなまじめな修行僧は何人くらいいるのかな」
無著「さあ、三百から五百人くらいといったところでしょうか。ところで和尚さん、あなたのところでは、仏法はどんな様子なのですか」
住職「『凡聖同居、龍蛇混雑』といったところだね」
無著「人数はどのくらいですか」
住職「『前三三、後三三』といったところだね」
一夜が明けて、無着さんはお礼を言って出発しました。
童子が門の外まで見送りました。無著さんが童子に問います。
無著「住職は『前三三、後三三』とおっしゃったけれど、これは何人のことなんだろうね」
童子は、「大徳」と呼びかけます(大徳とは、先輩の僧を尊敬して呼びかけるコトバ)。
無著が、「はい」と答えると、童子が言います。「これは何人なのでしょう」
無著は尋ねます。「以前来た時は、こんな寺はなかったように思うんだが、この寺はどういうお寺なんだろうか」
童子は後ろを指差します。無著が振り返ると、そこには寺がありませんでした。驚いて童子の方を向くと、童子もまた消え去って、どこにも見当たりませんでした。
この公案のポイントは文殊さんの『凡聖同居、龍蛇混雑』という言葉ですね。
若い頃、禅を共に学ぶ禅友がいて、後に彼は伝統ある禅道場の後継者となったそうなのですが、彼はよく、「あの老師はまだ悟っていない。あの人は悟りの段階が低い」などと、悟りという色眼鏡で、人の値打ちを判断するクセがありました。
これは、彼だけではなくて、禅をやっている人は、悟りの有無で人の優劣を決めつけてしまいがちなのです。
それは、戒律を守る、守らないで人の価値を判断したり、お金持ちか貧乏か、学歴があるかないかで人を差別するのと同種の間違いですね。
「ひとついのち」の自覚からながめると、人に上下、尊卑など一切ありません。
どの人も「人類の魂」が、進化成長のために、「この人がどうしても必要だから」と、地上に生み出された尊いいのちなのです。
他の人には、この人の身代わりは決して出来ません。
この人のワンピースが欠けただけで、人類進化達成図のジグソーパズルは完成出来ないのです。
ですから、あなたはあなたという宇宙に二つない貴重なあなたをしっかり精一杯生きなければなりませんね。
すべての人には、その人にしか果たせない「役割」が、人類の魂(ひとついのち)から分かち与えられています。
いろんな「役割」があります。しかし、どの「役割」にも、等しい価値があり、「役割」に大小、軽重などありません。
世界の政治を担う「役割」と、ひとりの子供を無事に成人させる「役割」を果たすのと、全く同等の価値のものなのです。
悟りを開くということでさえ、そんな「役割」のひとつにすぎません。その人が進化しているから、勝れているから悟ったというわけではありません。
私の場合なんかもそうです。
私は意志が弱いし、人嫌いだし、人間の器は小さいし・・・、あれやこれや、どう見ても「悟り役」、「縦糸役」にふさわしくないと思うんですが、なぜかこんな「役割」が割り当てられました。
そのことが、ずっと不思議で不思議で、「世の中にはもっと適任の人がたくさんいるのになあ、なんでこんなシンドイ役をボクが努めなあかんのかなあ」と時々愚痴っていました。
しかし、こんなアカンタレが「悟り役」をやっているのを見たり、接したりすると、皆さん、なんだかホッと安心されるようなのです。
こんな人でもやれるんだ、それなら私だってと、生きる勇気がでるようなのです。
指示役が頼りないものだから、とってもこの人に任せられないから、私がしっかりやらねばと自主的にしっかり考え、自分で判断決断して行動できる仲間が増えてきました。
そういう姿を見ていると、なるほどこれが「人類の魂」の計画の周到で、奥深いところなのかも知れないなあと思うのです。
ようするに、「ひとついのち」のメンバーひとり、ひとりには、等しい価値があり、優劣、高低はないのです。あるのはそれぞれの人の「役割」のみなのです。その「役割」にも、もちろんのこと、大小、尊卑はありません。
そんな真理を知らせるためには、私のようなアカンタレに「悟り役」をさせるのが一番いいのかも知れませんね。
「凡(普通の人)」を生きるのも「役割」、「聖」を生きるのも「役割」です。
「凡聖」いずれも同等の価値をもったいのちであり、「ひとついのち」の「あったかホームに同居」し、和気藹々と人類の進化のために協力しあっている兄弟・姉妹たちなのです。
以上で『凡聖同居』の意味がお分かりですね。
「俺たち(龍)とお前たち(蛇)では格が違うんだ。お前らは脇に避けて、俺たちに近寄るな」などといって、龍と蛇がお互いに隔離し、住み分けしているのではいけません。
おなじ、「ひとついのち」の「愛の抱擁」のもと、蛇(凡)も龍(聖)も、お互いの役割を果たすために仲良く入り乱れ、にぎやかに混じりあって生き生きと活動してゆくのです。そこに進化向上があるのです。
「あの人は悟っている、あの人はまだ迷い中だ」、あるいは、「あいつらは戒律を守らないから仏教徒ではない」などといった色眼鏡で、人や世界を見て差別し、非難することの「愚」を、文殊さんは無著さんに教えたかったのですね。(次回に続く)